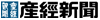若田さんは船長に、国産新型ロケット、ヒッグス粒子… 2013年の宇宙ニュース展望
2013年は、日本の宇宙開発にとって飛躍の年だ。宇宙飛行士の若田光一さん(49)が日本人として初めて船長を務める長期滞在の旅へ出発し、新型の国産ロケットが打ち上げられる。一方、米国の火星探査車や宇宙の謎に迫る「ヒッグス粒子」の動向、新発見の彗星(すいせい)が演出する天体ショーも見逃せない。宇宙分野の今年の注目ニュースを展望する。
■若田さんが日本人初の船長に
若田さんは年末、ロシアのソユーズ宇宙船に搭乗し、カザフスタンのバイコヌール宇宙基地から4度目の宇宙へ飛び立つ。自身2度目となる国際宇宙ステーション(ISS)での長期滞在だ。
滞在期間は前回(09年)の4カ月半より長い約半年。最初の約4カ月は通常のフライトエンジニアとしてISSの運用や科学実験に従事し、残る約2カ月はISSの船長を務める。
「コマンダー」と呼ばれる船長は重責だ。滞在する各国の飛行士を取りまとめ、安全確保と任務遂行を確実に達成することが求められる。船内での危機管理の責任者でもあり、宇宙ごみの衝突や火災、空気漏れなどさまざまな緊急事態が起きた場合、的確に指揮をとらなくてはならない。
ISSは米国とロシアの主導で運用されており、日本人が船長を任されるのは画期的なことだ。若田さんの能力が高く評価されたことの表れであり、これを機に日本人宇宙飛行士の国際的な役割と存在感が一段と増していくだろう。
若田さんは1992年に飛行士候補に選ばれ、翌年、飛行士に正式認定。96年、米スペースシャトルで初飛行し、2000年に2度目の飛行。09年にはISSで日本人初の長期滞在を行い、日本実験棟「きぼう」を完成させた。
ロボットアームのスペシャリストとして米航空宇宙局(NASA)の教官を務めた腕前を持つ。技術的な能力だけでなく、周囲との協調性やリーダーシップ、前向きで強い精神力とユーモアあふれる人柄など、多くの点で傑出した資質の持ち主だ。
数年前、ある宇宙関係者は「日本人で唯一、世界的な飛行士と呼べる人材。いずれISSの船長になるだろう」と評したが、それが間もなく現実になる。
2010年、NASAのISS運用部の部門長に就任。宇宙航空研究開発機構(JAXA)の宇宙飛行士グループ長を昨年8月まで務めるなど管理職としての経験も積み、日本のエースとして着実にキャリアを重ねてきた。
「任務の重大さをかみしめている。これまでの訓練や経験、JAXAやNASAでのマネジメント業務を通して学んだ知見を生かし全力で取り組んでいく」。約2年前、こうコメントした若田さん。日本人飛行士の歴史に残る大舞台が、いよいよ幕を開ける。
■新型ロケット「イプシロン」登場
今年は国産ロケットの新顔が登場する。JAXAが開発した小型ロケット「イプシロン」だ。日本の新型ロケットの初打ち上げは大型主力機のH2A(2001年)以来、実質的に12年ぶり。鹿児島県肝付町の内之浦宇宙空間観測所で8~9月に打ち上げる。
全長24・4メートル、重量91トンの3段式。国産ロケットの父、糸川英夫博士が開発した固体燃料ロケットの流れを受け継ぐ最新モデルだ。打ち上げ費用が高額だとして06年に“リストラ”された旧文部省宇宙科学研究所のM5ロケットの後継機に当たる。
低コストと効率的な運用が売り物だ。H2Aの機体側面にある固体ロケットブースターを1段目に転用することで、開発費を205億円に抑制。通常時の打ち上げ費用は38億円で、H2Aと比べて格段に安い。
運用面では打ち上げ前の機体点検を自動化でき、ノートパソコン数台で管制業務を行えるなど、ロケットの常識を覆す作業効率の高さを誇る。打ち上げ能力はH2Aの8分の1程度。H2Aを大型トラックに例えると、小回りの利く軽トラックといったところだ。
開発リーダーの森田泰弘JAXA教授は「これまでのロケットは性能重視で開発されてきたが、イプシロンは設備、運用面の効率性を重視した画期的なシステム」と自信を見せる。
H2Aや欧州のアリアン、ロシアのソユーズなど世界の主要ロケットは液体燃料を使っているが、「固体燃料ロケットはエンジンが不要で、部品点数は約半分で済むので開発期間が短い。世界一に立つ新しいロケットを開発しやすい」と強調する。
内之浦宇宙空間観測所は鹿児島県・大隅半島の東岸にある。1970年、日本初の人工衛星「おおすみ」を打ち上げた由緒ある発射場だ。人工衛星を搭載した国産ロケットはM5廃止以降、種子島宇宙センターで打ち上げられてきたが、今年は内之浦が久しぶりに脚光を浴びることになるだろう。
■火星探査車、生命の痕跡発見に期待
NASAの火星探査車「キュリオシティー」が順調に活動を続けている。昨年8月に着陸に成功した史上最大の探査車だ。これまでに太古の川が流れた跡や、火星の地表を覆う土が玄武岩質であることを発見した。
今年は探査の“本命”である生命の痕跡発見に期待が高まる。キュリオシティーは昨年12月、単純な有機物を見つけたが、火星由来の物質かどうかは分かっていない。この物質に含まれる炭素は、キュリオシティーが地球から持ち込んでしまった可能性が否定できないからだ。
惑星探査に詳しい会津大の寺薗淳也助教は「今回の有機物と似た物質が他の場所からも見つかれば、火星由来の可能性が高まる」と解説する。
キュリオシティーは今後、目的地の「シャープ山」に登りながら、試料の採取・分析を重ねていく。寺薗氏は「エキサイティングな発見は今年、十分期待できる。ただ、試料の分析結果は膨大な量になるため、解釈に数年かかる場合もある。成果をじっくり待ちたい」と話す。
■ヒッグス粒子、発見確定へ
すべての物質に質量(重さ)を与える謎の素粒子「ヒッグス粒子」の発見が目前に迫ってきた。日米欧などの国際チームによる実験データの分析は大詰めを迎えており、来月にも「発見」が正式発表される可能性がある。
実験に参加している日本グループ共同代表の小林富雄東大教授は「まだ結論づけることはできない。昨年12月までに得たデータを解析し、今年2月下旬以降に結論を発表することになりそうだ」と話す。
発見が最終的に確定すれば、物質の根源を探る素粒子物理学だけでなく、宇宙の謎の解明にも極めて重大な意味を持つ。ヒッグス粒子の存在を約50年前に予言した英物理学者、ピーター・ヒッグス博士らのノーベル賞受賞は確実だ。
スイス・ジュネーブ郊外にある欧州合同原子核研究所(CERN)の大型ハドロン衝突型加速器(LHC)を使った実験で昨年7月、ヒッグス粒子とみられる新粒子が見つかった。米科学誌サイエンスは昨年の10大ニュースのトップに選んだ。
なぜビッグニュースなのか。理由は2つある。
ヒッグス粒子は万物に重さを与える特別な素粒子で、「神の粒子」の異名をとる。物質の最小構成単位である素粒子は、その基本法則である「標準理論」で計17種類とされているが、ヒッグス粒子だけが見つかっていなかったのだ。
発見が確定すれば、科学者たちが約100年前から築き上げてきた物質の根源に関する理解の正しさが証明される。人類の英知の勝利といっていい。
もうひとつの理由は、ヒッグス粒子は宇宙の重大な謎を解明する手掛かりを与えてくれるからだ。17種類の素粒子がすべて発見されても、実はそれらは宇宙全体の物質の4%でしかない。残る23%の「暗黒物質」や、73%の「暗黒エネルギー」の正体はまったく分かっていないのだ。
ヒッグス粒子の性質を詳しく調べれば、宇宙の大半を占める未知の物質の正体が見えてくる。宇宙論に大きなインパクトを与えるのは確実で、今年は素粒子と宇宙論の融合による物理学の飛躍的な発展の第一歩になるだろう。
■過去数十年で最も明るい彗星「アイソン」
今年の天体ショーの筆頭格は晩秋の「アイソン彗星」だ。昨年9月に国際科学光学ネットワーク(ISON)のロシア観測チームが発見したばかりで、過去数十年で最も明るい満月のような明るさの彗星になるとも予想されている。
アイソン彗星は太陽にかなり接近するため、熱で蒸発するなどして消えてしまう懸念もある。しかし最近の研究では、氷などでできた本体は直径約3キロと十分に大きいので蒸発せず、太陽に突入することもなく、今年11月から12月にかけて観測できる可能性が高まっている。
記録に残る最も明るい彗星は1680年の「キルヒ彗星」で、それに匹敵する明るさになるといわれる。
天体観測に詳しい長野工業高等専門学校の大西浩次教授は「彗星の明るさの予想は外れることもあるが、肉眼で見える明るさにはなるだろう。もし本体が分裂すれば、逆にさらに明るくなる可能性もある」と説明する。
日本では明け方、東の空に位置するが、時期により見え方は大きく異なる。大西教授によると、11月1日ごろからは双眼鏡を使えば見られそう。太陽に最接近し最も輝く11月29日は尾が見える可能性はあるが、残念ながら本体は見られない。「11月中は一般の人が見やすい状態にはなりにくい」という。
その後は太陽から遠ざかり暗くなっていくものの、12月上旬から中旬の午前5~6時ごろが最も観測しやすい見通しだ。大西教授は「日中でも双眼鏡などで観測できる可能性があるが、太陽が視界に入ると失明の危険があるので注意してほしい」と呼び掛けている。
一方、アイソン彗星に話題を奪われがちだが、4月上旬から中旬にかけて観測しやすいと予想される「パンスターズ彗星」も楽しみだ。大西教授は「彗星は美しいだけでなく、太陽系形成の謎を解明する手掛かりを持っている。そんなことにも思いをはせて楽しんでほしい」と話す。